学生時代、何故か知らないけど解析力学の勉強はよくやった方だ。岩波テキストシリーズの『解析力学』(大貫義郎)とかランダウ・リフシッツの『力学』などを暇さえあれば読んでいた(そこまで読んでいなかったかな)。そんな防人だったので、生協の書籍部で
『微分形式による解析力学』(マグロウヒル 木村利栄/菅野礼司 著)
というタイトルの本を見つけたときは、中身もろくに見ずに購入してしまった。出だしの微分形式の所を読んで「フーン、なるほどね!」という感じになって、より本格的な微分形式の数学的な本に移行してしまい、肝心の核心部分を読まずに、しばらくの間本棚の肥やしになっていった。
その後、興味の対象は”ぶつり”から”つり”になり、北アルプスの溪を彷徨い歩く日々が続き、家にいるより谷にいる時間の方が多いのではという時期があった。そして、長い苦労の果てに(奥さんにとってだが)子供を授かるという幸運に恵まれたとき、これは”育児”に集中しないともったいないと思い、あっさりと”つり”から足を洗い、”育児”に専念するようになった。といっても、防人の場合、おむつ替えとかは苦手で奥さん任せであることが多く、また、夜泣きしても全く目が覚めないものだから、そういったことには全く役に立たなかった。ある時、「うちの子は全く夜泣きしなかったよなあ!」といったら、奥さんの目が吊り上がって「あなたが起きなかっただけじゃない。大変だったのよッ」とたしなめられたものだった。まあ、そんなこんなで家にいる時間が増えたものだから、何かしないと退屈であると思うようになり、そこで始めたのが解析力学の勉強だ。特に、時間を割いたのが学生時代にも興味があったラグランジアンの多様性、任意性?の疑問である。簡単な一次元の例で言うと、
等速直線運動の運動方程式:\(\ddot{x}=0\)
を与えるラグランジアン\(L\)はどのようなものがあるか?という問いは簡単で、
\[L_1=\frac{1}{2}\dot{x}^2\]
である。しかし、しばらく考えてみると、以下のようなヘンテコなラグランジアン\(L_2\)も存在していることに気が付く。
\[L_2=e^{a\dot{x}}\]
但し、\(a\)は定数である。このヘンテコラグランジアンをオイラー・ラグランジュ方程式にインプットすると、
\[0=\frac{d}{dt}\frac{\partial L_2}{\partial \dot{x}}-\frac{\partial L_2}{\partial x}
=a^2 e^{a\dot{x}}\ddot{x}\]
が恒等的に成り立つためには、等速直線運動の方程式:\(\ddot{x}=0\)が成り立つことになるわけだ。しかも、\(L_1\)と\(L_2\)は時間についての全微分項程度のズレではなく、根本的に異なるラグランジアン同士である。このように一つの運動方程式(二階微分方程式)を与える複数の異なるラグランジアンが存在しているが、これは何か数学的な意味があるのかどうか?また、どのようなタイプの運動方程式(微分方程式)にラグランジアンが存在しているのか?このようなことを解決しようと、一時期狂ったように計算をし、少し鬱っぽい状況まで追い込まれたのだった。そんな中、本棚から久しぶりに取り出した『微分形式による解析力学』をパラパラめくっていると、今自分が悩み苦しんでいるテーマがしっかり記述されていたことに気が付いたのである。長年そばに存在していたにもかかわらず、自分にとって興味あることが記述されていることに気が付かず放置状態にしていた我が身の愚かさを痛感したのであるが、今からでも遅くはないと思い、手にペンをもって、計算過程を追い、精読を開始したのだった。それ以降、育児の合間の勉強時間は極めて有意義な時間へと変貌していった。

当時はマグロウヒルから出版されていたが、現在は吉岡書店から売られているようだ。表紙も全然違うデザインになった。防人的にはこの雰囲気が好きだ。同じシリーズの中に、"トポロジーと幾何学"とか"量子重力理論"なんていう本もあったよな。

計算ノートも造ったが、本にも補った計算過程を書き込んだり、該当する論文の情報を書き込んだりしたのだった。いつもこの本を持ち歩き、スタバ、コメダや電車の中など至る所で、暇さえあれば読んでいたものだ。
運動方程式(二階微分方程式)
\[A(x, \dot{x},t)\ddot{x}+B(x, \dot{x}, t)=0\]
がVariational(力学系または二階微分方程式系が最小作用の原理の観点から定式化可能)であるとは、
\[A\ddot{x}+B
=\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}-\frac{\partial L}{\partial x}
\]
なるラグランジアン\(L=L(x, \dot{x}, t)\)が存在することであった。そして、\(A\)、\(B\)が以下のHelmholtz condition(一次元の楽チンバージョン)を満たせばラグランジアン\(L\)が存在することがわかるわけだった。それは、
\[\frac{\partial B}{\partial \dot{x}}=\left( \dot{x}\frac{\partial}{\partial x}+\frac{\partial}{\partial t}\right) A ★ \]
というものである(後々の回で『微分形式による解析力学』のやり方に添って導出は説明する。これはとても長い話になるのよねぇー!)。さて、今回は空気抵抗型の運動方程式
\[ m\ddot{x}=-kv-mg \]
のラグランジアンについて考えてみよう。この両辺を\(m\)で割って、
\[\ddot{x}+\frac{1}{\tau}\dot{x}+g=0\]
但し、\(\tau\)は\(\displaystyle \tau=\frac{m}{k}\)と置いたもので、緩和時間と呼ばれている。さて、この微分方程式は\(\displaystyle A=1\)、\(\displaystyle B=\frac{1}{\tau}\dot{x}+g\)であるから、上記のHelmholtz condition★は
左辺が\(\displaystyle \frac{\partial B}{\partial \dot{x}}=\frac{1}{\tau}\)
右辺が\(\displaystyle \left( \dot{x}\frac{\partial}{\partial x}+\frac{\partial}{\partial t}\right) A =0\)
よりHelmholtz condition★を満たしていない。と言うことは、空気抵抗型の運動方程式にはラグランジアンが存在していないのか?解析力学の土台に乗せることが出来ないのか?実はここで諦めるのは時期尚早である。一般的に、微分方程式
\[A(x, \dot{x},t)\ddot{x}+B(x, \dot{x}, t)=0\]
がHelmholtz condition★を満たさなかったとしても、両辺に\(N\)を乗じた、
\[A'(x, \dot{x},t)\ddot{x}+B'(x, \dot{x}, t)=0\]
が満たしていればラグランジアンは構成できる。但し、\(A’=NA\)、\(B’=NB\)であり、この\(\displaystyle N=N(x, \dot{x}, t)\)をIntegrating factor(積分因子)という。以下これをN因子と呼ぶことにする。空気抵抗型の微分方程式の場合、つまり、\(A’=NA=N \)、\(B’=NB=N\left(\frac{1}{\tau}\dot{x}+g\right)\)について、N因子が満たすべき方程式を導出しよう。Helmholtz condition★より、
\(\displaystyle \left( \dot{x}\frac{\partial}{\partial x}+\frac{\partial}{\partial t}\right) A’ =\frac{\partial B’}{\partial \dot{x}}\)
\(\displaystyle \left( \dot{x}\frac{\partial N}{\partial x}+\frac{\partial N}{\partial t}\right) =\frac{\partial (NB)}{\partial \dot{x}}=\frac{\partial N}{\partial \dot{x}}B+N\frac{\partial B}{\partial \dot{x}} \)
\(\displaystyle =\frac{\partial N}{\partial \dot{x}}\left(\frac{1}{\tau}\dot{x}+g\right)+N\frac{1}{\tau}\)
以上より、N因子の満たす一階偏微分方程式
\[-\frac{1}{\tau}N+vN_x -\left(\frac{1}{\tau}\dot{x}+g\right)N_v+N_t=0 ① \]
を得る。但し、\(\displaystyle v=\dot{x}\)、\(\displaystyle N_x=\frac{\partial N}{\partial x}\)、\(\displaystyle N_v=\frac{\partial N}{\partial v}\)、\(\displaystyle N_t=\frac{\partial N}{\partial t}\)と置いた。我々はこの偏微分方程式の解\(N\)を発見すれば、そこから空気抵抗型の運動についてのラグランジアンを構成できるのである。一般に、シュレーディンガー方程式、波動方程式とか熱伝導方程式などの偏微分方程式はよく書物で見かけるが、このような一階偏微分方程式の解き方などは学んだこともなかった。そこで、『微分方程式 小堀 憲著 朝倉数学講座』の第八章を勉強し、その後、『詳解 微分方程式演習 共立出版』で何問か問題演習をこなし、自信をつけてから上記の”N因子”についての一階偏微分方程式を解きにかかることにしたのだった。

一階偏微分方程式を解くことになって、名古屋鶴舞の古本屋さんで見つけた本。N因子の決定においてはとても役に立つ。

これは学生時代に買って、ほとんど使わずにいた本だ。こんなところで役に立つとは!これだから本は捨てられないね。
以下では上記の本達に載っている特性曲線法というやり方で、N因子を求めることにしよう。まず、\(\displaystyle N=N(x, \dot{x}, t)\)のone formを考えて、以下のように変形する。
\(\displaystyle dN=\frac{\partial N}{\partial x}dx+\frac{\partial N}{\partial v}dv+\frac{\partial N}{\partial t}dt\)
⇔ \(\displaystyle -dN+N_x dx+N_v dv+N_t dt=0 \)
⇔ \(\displaystyle \left(dN, dx, dv, dt\right)\cdot \left(-1, N_x, N_v, N_t \right)=0 \)
一方、上記①のN因子の一階偏微分方程式を同様に変形する。
\(\displaystyle \left(\frac{1}{\tau}N, v, -\left(\frac{1}{\tau}v+g\right), 1\right)\cdot \left(-1, N_x, N_v, N_t \right)=0 \)
よって、
\(\displaystyle \left(dN, dx, dv, dt\right)\parallel \left(\frac{1}{\tau}N, v, -\left(\frac{1}{\tau}v+g\right), 1\right)\)
⇔ \(\displaystyle \tau \frac{dN}{N}=\frac{dx}{v}=\frac{dv}{-\frac{1}{\tau}v-g}=\frac{dt}{1}(=\lambda \):一定\( ) \)
これより、上記①の偏微分方程式は以下の三つの常微分方程式に帰着される。
〈Ⅰ〉\(\displaystyle \frac{dx}{v}=\frac{dv}{-\frac{1}{\tau}v-g} \)を考える。以下では、\(\displaystyle (v+\tau g)_v=\frac{d}{dv} (v+\tau g)\) である。
\(\displaystyle dx=\frac{vdv}{-\frac{1}{\tau}v-g}=-\frac{\tau v dv}{v+\tau g}= -\frac{\tau (v+\tau g)-\tau^2 g}{v+\tau g}dv \)
\(\displaystyle =-\left\{\tau-\tau^2 g \frac{(v+g\tau)_v}{v+\tau g}\right\}dv \)
この両辺を積分すると、
\[x=-\tau v+\tau^2 g \ln(v+\tau g)+c\]
となる。ここで、両辺を定数\(-\tau^2 g\)で割って、\(\displaystyle c_1=-\frac{c}{\tau^2 g}\)と置き直すと、
\[c_1=-\frac{1}{\tau g}\left(\frac{1}{\tau}x+v \right)+\ln(v+\tau g) \]
〈Ⅱ〉\(\displaystyle \frac{dv}{-\frac{1}{\tau}v-g}=\frac{dt}{1} \)を考える。
\(\displaystyle dt=-\frac{\tau}{v+\tau g}dv=-\frac{\tau(v+\tau g)_v}{v+\tau g}dv =-\tau \left(\ln(v+\tau g)\right)_v\)
なので、両辺を積分すると(積分定数は\(c_2\)とする)
\[c_2=\frac{t}{\tau}+\ln(v+\tau g)\]
〈Ⅲ〉\(\displaystyle \frac{dN}{N}=\frac{dv}{-v-\tau g}=-\frac{1}{v+\tau g}dv \)
なので両辺を積分すると、\(\displaystyle \ln N=-\ln(v+\tau g)+C \)となるので、
\(\displaystyle C=\ln\left\{N\cdot (v+\tau g)\right\}\) より \(\displaystyle c_3= N\cdot (v+\tau g)\)
とまあ、一応積分が出来たわけだが、この後どうするのかと言うことを一般論でまず説明しておこう。
一般に、微分方程式の積分結果が
\(\displaystyle c_1=\phi_1(t, x, v, N)\)、\(\displaystyle c_2=\phi_2(t, x, v, N )\)、\(\displaystyle c_3=\phi_3(t, x, v, N)\) …②
であったとしよう。\(t=0\)での初期条件(というより境界条件)を\(G(0, x, v, N)=0\)とする。この関数\(G\)は任意である。偏微分方程式の初期条件は境界条件であり、それは関数で表記されていて、今の場合は\(G(0, x, v, N)=0\)という訳だ。上記の②式たちを\(t=0\)で\(x, v, N\)について解いたとして、それらを
\(\displaystyle x=\varphi_1(c_1, c_2, c_3)\)、\(\displaystyle v=\varphi_2(c_1, c_2, c_3)\)、\(\displaystyle N=\varphi_3(c_1, c_2, c_3)\) …②
として、これらを\(G(0, x, v, N)=0\)へ代入したものを\(g(c_1, c_2, c_3)=0\)(または、\(c_3\)について解いたとして、\(c_3=f(c_1, c_2)\))とする。ここで、\(g\)は任意の\(G\)に対応していることに注意しよう(つまり、\(g\)や\(f\)も任意なのである)。よって、一般解は、
\[g\left(\phi_1(t, x, v, N), \phi_2(t, x, v, N),\phi_2(t, x, v, N), \right)=0\]
となる(またはこれを\(N\)について解いたものである)。
今回の例では、\(c_3=f(c_1, c_2)\)とすると、
\(\displaystyle N\cdot (v+\tau g)=c_3=f(c_1, c_2)\) より、\(\displaystyle N=\frac{f(c_1, c_2)}{v+\tau g}\)
と積分因子Nが求まったことになる。但し、
\(\displaystyle c_1=-\frac{1}{\tau g}\left(\frac{1}{\tau}x+v \right)+\ln(v+\tau g)\)
\(\displaystyle c_2=\frac{t}{\tau}+\ln(v+\tau g)\)
である。次に我々がやることは任意関数\(f\)の形を決めて、ラグランジアンを構成するという極めて楽しい(コレクター気分満点)計算なのであるが、これは次回に譲ることにして、今日はこれにておしまいにしますか。
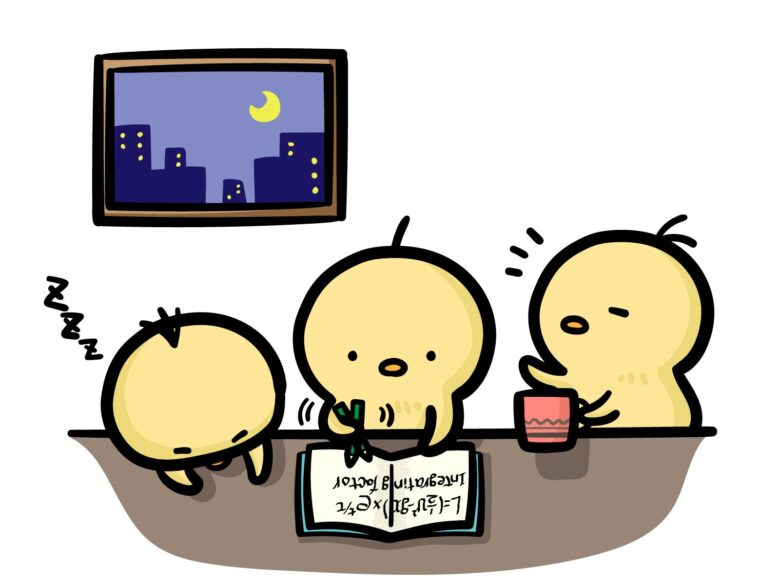


コメント