バンガロー生活の習慣か、それとも昨日わずかなお酒で酔いまくり爆睡してしまったからか、早朝5時台には目が覚めてしまった防人である。Ya氏と共に露天風呂に浸かり、その後はまったりと朝食を頂いた。自分ですべてやらなくてはならないバンガロー生活と180度異なり、上げ膳据え膳で自らは何もやる必要もなく、ただ受身的にサービスを享受していると、何だか攻めの姿勢が衰えて来て、消極的になって行くように思える。のんびりと準備をして9時に温泉旅館を出発した。
安達太良山と吾妻山の間を抜ける国道115号線を走り、途中から県道70号線に入り、裏磐梯の秋元湖を目指す。今日は「裏磐梯の湖群に流れ込むどこかの沢で釣りでもしようかなあ」というなんともいい加減な計画なのである。まず、吾妻山から流れてくる大倉川はそれなりの規模で釣りになりそうだが、橋から見た堰堤群、薬師谷に比べて精彩が欠いているような感じがして釣りするのをためらってしまった。次に、中津川渓谷。ここは釣りになりそうだし、渓谷美としては申し分ないが、遡行が大変そうで、すっかり消極的になってしまっている我々は釣りをしようという気にならない。その上、沢登教室の20人ぐらいの集団が入渓していくのを見て、あっさりと諦めてしまった。その後は小野川湖を見て回り、曽原湖畔にあったキャンプ場(磐梯高原曽原湖キャンプ場)の受付の人に
「渓流釣りに良い川はないですかねェー?」
と聞くと、
「渓流釣り?イヤーないねェー。檜原湖でのブラックバス釣りは有名だけど…、渓流ねえぇー」
と消極的な答え。我々の気分もより消極的となり檜原湖をぐるりと一周。途中、早稲沢、大川入川を見て回るも、渓相いまいち(というより我々のやる気いまいちということか)。釣りの代わりに道の駅”裏磐梯”にてアイスクリームを食べて己の実存的意義を確認するという体たらくぶり。釣り人失格である。アイスを食べながら、
「これらの湖はダム湖ではないんですねぇー?」
という防人の間の抜けた質問に、郡山出身のYa氏は、
「何を言っているゥー、ポン助(防人の幼少期のあだ名)ッ!これらの湖は磐梯山の山体崩落で明治期にできたんだぞゥーッ」
とのこと。なんと、これらはたった140年くらい前にできた湖群であったとは意外や意外!

明治期の山体崩落で、檜原村は直撃を受け、多くの村人の命が奪われたらしい。

猪苗代湖と別れを告げ御霊櫃峠(ごれいびつとうげ)に向かう。
今から5万年前の山体崩壊は磐梯山の表側(表磐梯)で起こり、その時川をせき止められて形成された湖が猪苗代湖である。そして、今から140年ほど前の1888年(明治21年)7月15日朝7時30分ごろ、磐梯山は大音響とともに爆発(水蒸気爆発)。当時磐梯山は大磐梯、小磐梯などの四つの成層火山が寄り添い、あたかも一つの山のようになっていたのだが、この爆発で、北側の小磐梯が崩壊。磐梯山北側にあった上ノ湯、中ノ湯、下ノ湯の温泉湯治客、更に麓の檜原村の住人は逃げる暇もなくこの崩壊の土砂に飲み込まれ、300名近い死者が出たという。更に、この崩壊に伴う土砂は長瀬川の水と合わさることで泥流化し、川を流れ下る。この長瀬川下流にあった長坂集落の住人は、磐梯山の噴煙に驚いて、これと反対の長瀬川方面に避難を開始し、この泥流に飲み込まれてしまった。長坂集落では避難をしなかった住民が生き残り、避難した住人は皆死亡となったらしい(諸説あり)。前兆現象としては、噴火の一週間前から有感地震が増加、当日の7時頃からは鳴動、地震が連続化したという。また、中ノ湯温泉の湯治客の中で生還した鶴巻良尊の証言によれば、噴火前日の14日(晴天)の午前10時ごろから湯量が減少し、同日午後3時からは目覚ましく湯量減少したいう。しかし、この温泉は晴天で湯量減り、雨が降ると湯量増えるという感じで、日頃から湯量の増減があったこともあり、誰もが異常とは思わなかったようだ。結局、この噴火の犠牲者は500名近い数となり、明治以降の火山災害で最大の死者数となった。1877年(明治10年)が西郷隆盛の西南戦争(日本最後の内戦)、それからわずか11年後の会津(戊辰戦争では幕府軍側で朝敵とされた)での大災害であったが、皇室から恩賜金が下賜され、政府が災害救援対策に乗り出した。また、報道機関主導の広範囲かつ大規模な義援金の募集などとともに、これまでの幕藩体制のもと藩中心の狭い地域の中で完結しがちであった人々の意識から、国家意識を育てる一つの契機となった災害でもあったようだ。現在の裏磐梯は300近い湖沼が点在し、緑豊かな森が広がり、140年前の山体崩落の大災害を想像することは難しい。更に、防人が訪れた時は、磐梯山はず~っと雲に隠れ、結局、次の日も含めて一度も拝むことが出来なかった(だから磐梯山の写真は一枚もない)。もし裏磐梯が見れたなら、そこには大崩落の跡を見ることが出来たはずなので、それはまた次の機会に取っておけという磐梯山のお告げなのかもしれないね。
結局、釣りについて消極的な我々は、良い川を見つけられずにただドライブを続けるだけだった。裏磐梯地域をドライブして、表磐梯に出て猪苗代湖でバス釣りと思ったが、雨が降り出したり、車の駐車場所が見つからなかったりと色々と釣らないための言い訳ばかりだけが見つかり、時間が過ぎ去っていった。そこで、郡山に向けて、御霊櫃峠(ごれいびつとうげ)を越えていこうということになり、猪苗代湖畔から離脱することにした。

峠の駐車場にさきもりちゃんを停めて、大将旗山方面を見る。

公衆トイレの向こうには福島県最大の町(⁉)である郡山市がある。
白河から会津若松に入るには(つまり、官軍が会津若松を攻めるためには)、猪苗代湖とその周辺の山々が自然の障壁となっていた。南から馬入峠・勢至堂峠・諏訪峠・三森峠・御霊櫃峠・中山峠・母成峠と言う峠越えの道があったが、多くの軍勢が越せるのは勢至堂峠・母成峠であったらしい。そこで、防衛隊の主力をこの二つの峠に注いだが、それ以外の峠も防衛の必要性があったのだろう。この御霊櫃峠にも会津軍による土塁などが残っているので、戊辰戦争の当時戦闘とかあったのかも。峠の駐車場にさきもりちゃんを停めて、Ya氏、防人それと防人の化身のオオトリ様(防人アバター)を引き連れて、トレイルを大将旗山方向に歩く。途中で、下山して来たテキサス出身のアメリカ人は興味ありげに防人アバターをチラチラ見ていたが、彼はバイクを日本で買って、沖縄から北海道までの往復旅を楽しんでいる途中だと言っていた。小高い丘からは郡山が一望でき、官軍の動きも手に取るようにわかる。我々も会津をディフェンダーとして防衛しなくてはいけないので(何故にいきなりそうなった?)、郡山方面を目を凝らして眺めた。また、反対側は猪苗代湖の一部が切り取られた景色が目に飛び込んできて、これまた素晴らしい。

稜線上のトレイルの至る所にヤマユリが咲いていて、とても美しい。

郡山市を見下ろす防人。これから峠を下り、Ya氏の故郷郡山に向かう。

迫りくる官軍との戦いに、鶴ヶ城防衛という防人としての意識を高める防人!?

会津若松方面を眺める。眼下の湖は、ドライブしてきた猪苗代湖だ。
会津藩の松平容保は京都守護職にあって、新選組とかを使って長州をいじめていたので、長州からしたら会津藩は憎き存在だったのだろう。薩長は討幕に向けてこぶしを振り上げ戦を始めようとしたが、徳川慶喜は大阪城、江戸城ともに無血開城してしまったので、こぶしのおろし所を見つけあぐねていた。そうしたところに会津は奥羽越列藩同盟などを組織して反抗の気配丸出しだったので、薩長としては大義名分も揃い、積年の恨みもあったことから徹底的にたたいてしまったのだろう。燃え盛る鶴ヶ城を目の当たりにして、飯盛山にて自刃した白虎隊は有名だが(1986年年末時代劇スペシャル”白虎隊”は夢中で見たなあ。途中からみんな殺されたり、自害したり大変なドラマだった。堀内孝雄の”愛しき日々”という曲をこのドラマで初めて知ったのだった)、Ya氏の話によると、これ以外にも朱雀隊(18歳~35歳までの藩の男子から構成。正規軍の主力)、青龍隊(36歳から49歳までの藩士の男子から構成。国境防衛が任務だが、戊辰戦争では朱雀隊に次ぐ主力として各地で奮戦)、玄武隊(50歳以上の藩士で構成。予備隊。防人はここかあ!戊辰戦争では強清水など城下周辺で奮戦)もあり、みんな全滅したらしい。ちなみに、白虎隊は16歳から17歳までの藩士の男子で構成されていて、藩主の親衛隊であったとか。各峠を官軍に突破され、藩主の容保はこの白虎隊にも出撃命令をだしたようだ。飯盛山での悲劇は白虎隊の士中二番隊の少年20人だったが、その中の一人、飯沼貞吉のみ蘇生して、後世に白虎隊の悲劇を伝えたことにより白虎隊だけが有名になったらしい。
御霊櫃峠の防衛を完了した我々は(もう終わったんかいッ!)、峠を郡山方面に降りて、途中、Ya氏の母校福島県立安積高等学校(ふくしまけんりつ あさかこうとうがっこう)の旧本館を見学したが、残念なことに耐震補強工事中で足場とかが組まれていて、中も入れなかった。工事完了には数年かかるらしい。その後は郡山市内のYa氏の実家に行って、Ya氏の奥様や妹さんに会い、ワイワイガヤガヤと焼肉キングに繰り出して楽しい夕飯タイム。Ya氏の実家に戻ってからも陸奥追悼旅行の話で盛り上がり、気がついたら夜半過ぎ。明日は日光でてんぷらさんに会い(オフ会か!)、その後は八ヶ岳の別荘まで下道移動である。そろそろ寝なくては明日に影響するね!

重要文化財「旧福島県尋常中学校本館」は明治22年(1889)創建。ということは、1888年が磐梯山の大崩落だから、その次の年に完成しているわけだね。洋風建築のたたずまいを当時のままに、世紀を超えて今なお現存する貴重な建造物であり、Ya氏はこの貴重な校舎で学んだとのこと。

オヤジ追悼の東北の旅の最後の夜は、晩年のオヤジが愛した焼肉キングに行った。Ya氏の奥様、Ya氏の妹さん(郡山在住)と4人で食べまくったのだった。楽しいひと時であった。
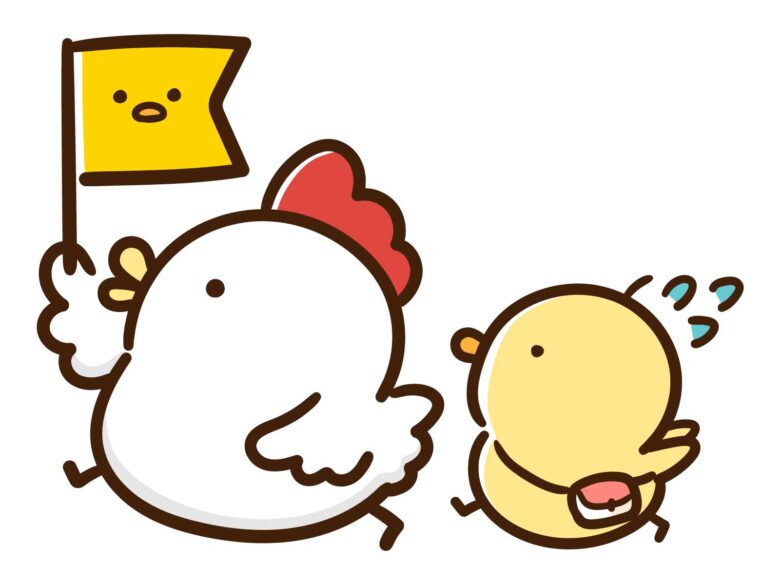


コメント