バンガロー生活も三日目ともなると体が慣れてくる。朝起きて、朝食を作り、歯磨きして、釣支度をする。そして、川を歩き、ぬめりけのある石でコケて、毛バリを流し、そして、イワナを釣る。これらが日常となり、イワナが釣れてもそれほどの感情の爆発が起こるわけでもなく、淡々と毛バリを投げ込むのである。そして、昼頃になると、谷から上がり峠を越えて隣谷の横沢温泉に入りに行く。今日の温泉番はお姉さんではなく、東北弁ガンガンのおばちゃんである。よくわからずお金を払い、お風呂に浸かる。そう言えば、昨日のお姉さんがこの近くに”かつ丼”の美味しい店があると言っていたなあ。Ya氏と話し合い、今日はそこで昼飯を食べることにした。しかし、時はすでに2時。かつ丼の”うちさわ”というお店の閉店時間が3時なので、急がなくてはならない。お風呂から出たばかりであるが、慌ただしく温泉宿を後にする。

今日も薬師川の流れは清冽である。天気も安定して晴れの日が続く。

薬師川を釣り上がるYa氏。オヤジとの付き合いは息子の防人以上に長いかもしれない。

かなり良いサイズのイワナ君。手ごたえよく、取り込むのに苦戦させられた。

ふと見上げると、頭上には夏の空が広がっていた。夏は暑く、薬師川は冷たく最高だね。
14時30分、閉伊川水系で一番おいしいかつ丼屋さん(他にもかつ丼屋さんあるのかね?)に到着する。どうにか間に合ったようだ。Ya氏はお蕎麦とかつ丼のセットを注文する。防人はかつ丼を堪能したかったので、大盛りかつ丼を注文。ボリューム感たっぷりで、味もしっかり甘辛いたれと卵が絡みつき最高である。十分お腹がいっぱいとなり、後は宮古へ今宵の夕飯の買い出しに行くのみである。釣りをして、お風呂に入り、昼飯をたらふく食べた後は、普通にやることと言えば昼寝である。Ya氏は隣の助手席で気持ちよさそうに眠り出した。そういう防人も、ステアリングを持つ手が重くなり、瞼が下がり始めた。そのうちに、直進しているつもりがセンターラインに寄り出したり、スピードが増減しだして、居眠り運転の兆候が明白に出始めた。窓を開け、ほっぺを引っ叩き、「ウオッー」と叫ぶ。隣のYa氏が飛び起きて何事かと周囲を見渡している。この行為でどうにか復活した防人は無事に宮古の業務スーパーマルイチに到着。今夜はキーマカレーにするので、ひき肉を買い、更にはズッキーニやアスパラガスなども買い、野菜の源の確保もしっかりすることにした。スーパーを出る時、ふと、我々は宮古の海を見ていないということに気が付き、
「それなら、浄土ヶ浜に行ってみましょう」
ということになった。ここは、確か小学生の時に薬師谷に来た時、おふくろと来た記憶があるのだ。

一番人気のメニューのようで、かつ丼のお蕎麦セット。お蕎麦好きには、ざる蕎麦の2.5倍盛りの噴火盛りも出来るようだ。

甘辛いたれと卵がカツに絡みついて最高のかつ丼でした。ここに住んでいたなら、週に一回は訪れるお店になるだろう。流石に、名古屋からだと数年に一回だろうけど。

小学生の頃、ここの浜辺で確か水遊びをしたのだった。宮古の旅館でマグロ?カツオ?のたたき?を食べすぎて、気持ち悪くなったような、ならなかったような。

この流紋岩の浸食奇岩群は素晴らしいの一言。まさに、極楽浄土の雰囲気が漂うが、観光客も多いので、放送とか入って、そういう意味では極楽とは程遠いかも。
第一駐車場にさきもりちゃんを駐車し、そこからは遊歩道を歩いて、一番奥の遊泳場まで行ってみた。たしか、ここで遊んだ記憶があるが、当時のイメージでは、沖合に見える奇岩があったという記憶が全くない。恐らく水遊びに夢中になり、周囲の景色なんか見ていなかったのだろう。この白い色の浸食された奇岩群は火成岩の流紋岩であるらしい。流紋岩は、マグマが流れつつ冷えて固まってできたもので、火成岩の中の火山岩に分類される石だ。流紋岩のなかには、このマグマの流れ模様が(流離構造)が、しま模様として見られるものもあって、流紋岩と言う名前は、このしま模様に由来しているらしい。この浄土ヶ浜の地名は、宮古山常安寺七世の霊鏡竜湖(1727年没)が、この浸食された流紋岩の風景を見て「さながら極楽浄土のごとし」と感嘆したことから名付けられたと言われている。薬師谷から流れ下ってきたオヤジの魂は、この浄土ヶ浜から極楽浄土に登って行くのだろうか。そういう意味では、薬師谷は生前も死後もオヤジにとって最高の場所だと思うのだった。
ふと気が付くと時間は夕方4時だ。我々は昨日で薪を使い果たしていて、今日は薪を手に入れないといけない。宮古にも薪屋さんがあるようだが、やっているかどうか怪しい。となると、早池峰山荘で買うことになるが、山荘は5時で閉店である。一時間弱で戻れるか!浄土ヶ浜の駐車場を4時5分に急発進。往路のウトウトポヨヨン運転とは対照的に、スポーツモードガンガン運転となる防人。コーナーを攻め、林道を駆け抜ける。このような時に、ディフェンダー90ガソリンエンジンの身軽さは心地よい。早池峰山荘には4時55分に到着して、店じまいしようとしている管理人の方からギリギリ薪を購入することに成功した。昼飯といい、薪といい、今日は時間制限を受けたドライブを余儀なくされた一日であったなあ(良い子は決して真似しないようにね)。

夕方5時ごろ、早池峰山荘から見た眺め。キャンプサイトの後方には雄大な早池峰山が横たわる。

新しい薪を買い、そこに火をつけるために立ち働くYa氏。それを、監視する防人。彼らの背後には、湿った服などの物干しに使われて迷惑気なさきもりちゃんがいる。

薪に火がついて、安定化したのを満足する防人。炎を眺めながら、浄土ヶ浜を思い出し、極楽浄土を妄想するのである。さーて、夕飯の準備に取り掛かるかなあ。
バンガローに戻り、新しい薪に火を起こす作業に専念するYa氏。ご飯を研ぎ浸漬し、キーマカレーのひき肉を炒め、アスパラガスをゆで、ズッキーニを炒める。二時間ほどで夕飯を完成させ、それを食した後は、いつも通り、お酒を飲みながらののんびりタイムだ。今日はオヤジの思い出話というより、Ya氏の学生時代の山岳部の過酷な経験の話で盛り上がった。
どの部活もそうかもしれないが、新入生勧誘の時は先輩はとても優しく接してくれて、ご飯とかおごってくれて至れり尽くせりの待遇に騙されて入部を決めてしまう。そして、5月に第一回の山行が行われると山岳部の現実を知ることになるらしい。重い荷物を背負って(女性部員だからと言って容赦はない)、登山道を登り、汗だくになるがお風呂なんかない。もちろんトイレは自然の中で行う(キジ撃ちという)のだけど、これも女性だからと言っての配慮はない。また、当時は(僕の時代もそうだが)「水を飲んだらバテるから、運動中は水を飲むな」と言われた。縦走中に喉がカラカラになったからと言って、水は乾いた喉を湿らす程度しか与えられない(まあ、テン場に到着したらがぶがぶ飲ませてもらえるらしいが)。そして、数日山を縦走していると、自分自身の体から発せられる今まで経験したことが無いような悪臭を感じるようになるらしい。下山して温泉に入れたなら良いが、時には入ることが出来ないまま、帰路の電車に乗ることになる。そうすると、山岳部員が乗り込んできた車両は強烈な悪臭で満たされることになり、他の客は皆逃げ出していくようだ。そんなわけで、その車両は山岳部のみの特別車両となり、東京まで占有できるとか。5月のこの山行が終わると、入部した女性部員のほとんどは部を辞めるそうだ。しかし、その中で残った女性部員は男性部員よりはるかにたくましいらしい(当たり前だよな)。
この話を聞いた時、ふと、昔黒部上之廊下を遡行した時のことを思い出した。その時は上之廊下(黒部ダムのバックウォーターの東沢小屋という小屋から薬師沢出会いまでの間を下流側から上之廊下・中之廊下・奥之廊下という)から最源流までを一週間以上かけて遡行したのだ。最後、源流部まで来た頃には食料もなくなり、イワナも食べ飽きて、三俣山荘という山小屋に一泊しようということになった。受付に行くと、部屋はいっぱい(一つの布団に二人で寝る状態)だから、テントか山荘の廊下で寝てくれと言われた。まあ、テント出すのも面倒だし、テント生活も飽きてきたので、山小屋の廊下でシュラフで寝ますということになった。この時の久しぶりに食べた山小屋の人間らしい夕食の美味しかったこと。6~7杯ぐらいご飯をお替りした記憶がある。さて、我々は黒部川からやってきた沢登りの登山者なのである。だから、一般登山者に迷惑がかかるような悪臭は放っていなかった。毎日渓水に浸かり、泳いで廊下帯を突破し、滝場では頭から水をかぶり、夜の焚火では煙で衣服を燻して心地よい状態を保ち、それはそれは清潔な状態で行動していたのだ。そのため、山小屋の一般登山者の方々とも極めて良好な関係を保つことが出来た。夕飯も終わり、シュラフに入り水平な床の上で(遡行中は河原のごつごつした石の上で寝ていたのでね)寝られることの幸せを噛みしめながら深い眠りについたはずだった。それが、早朝3時半ごろ、何かポロポロと粉のようなものが顔に降りかかってくることに気が付いて、また、周囲がざわついていることもあって眠りから覚めてしまった。薄目を開けてみると、大学山岳部の学生たちが山荘で作ってもらったお弁当をもらうため列をなして待っていたのだ。そして、各自からは強烈な悪臭が立ち込めていて、みんなどこぞをボリボリ掻いている。そして、丁度僕の顔の真上には一人の部員がいて、彼の手が股をボリボリかいている状態が観察された。その彼の股から剥がれ落ちた垢?、皮膚?が重力の効果を受けて、しかし、最終的には空気抵抗力と平衡状態となって一定の速度で僕の顔面に降り注いでいたというわけだ。この地獄絵巻を目の当たりにして、言葉を失った僕は、ミノムシのようにシュラフの中に完全に顔を引っ込めて、下を向いたまま鼻をつまんだ状態でしばし耐えがたきを耐えたのだった。弁当の受け渡しは30分ぐらいの間だったのだろうけど、僕には数時間の長い苦痛の時間に感じられた。その後は、静寂が戻り、匂いも徐々に拡散し、再び眠りにつくことが出来たのであったが、この時の降りかかってきた垢の感触、そして匂いは今でも忘れることが出来ない。
山人たちの歌で、「雪よ岩よ われらが宿りー 俺たちゃー 町には住めないからにー」というのがあるが、あんな悪臭で街に来られたら、町の人間はたまったものじゃあないから、「山男は街に来ないでくれ」という切実な願いの裏返しの表現が歌に込められているのではないかと思ってしまった。兎に角、このYa氏は大学時代、200日くらい山に籠っていて、南アルプスの山小屋でも働いたり、山岳救助に関わったりと山漬けの学生時代を送っていて、大学4年の卒業研究でたまたまオヤジのゼミに転がり込んできたらしい。というのも、研究室に大量に存在した児童文学の本を、東京のアパートに運ぶ学生をオヤジが募集していて、重たい荷物を運搬することの能力が長けている山岳部員のYa氏が紹介されたというのが事の真相のようだが。そして、その後のオヤジとの長ーい付き合いが始まったというわけだ。おかげで、Ya氏は息子の防人よりオヤジの生態を熟知することになったのである。
明日はいよいよ薬師谷とも別れを告げ、福島の土湯温泉で旅館に泊まり、上げ膳据え膳ののんびり温泉タイムである。楽しみだなあー!
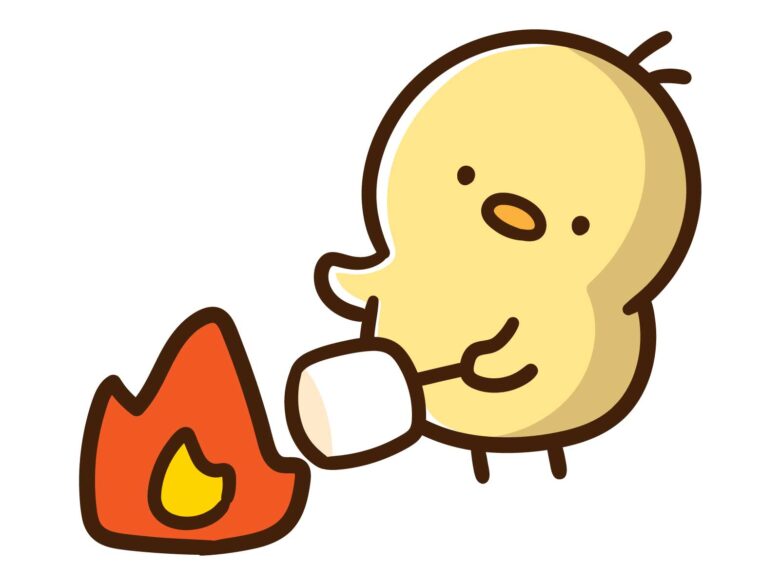


コメント